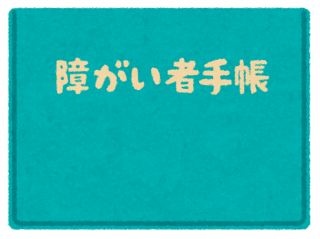8月13日は怪談の日! 怪談に隠された真理とは!?

こんにちは、さんちゃんです。
本日8月13日は「怪談の日」です。
怪談の日
昭和から平成の中頃くらいまでは、この時期になると心霊写真やお化け、怪談話などがテレビ番組でとく特集されていました。
怪談話といえば、独特の語り口で一世を風靡した稲川淳二さんが有名です。
その稲川淳二さんが命名したのが「怪談の日」です。
怪談の日
「怪談」をエンターテインメントとして確立した稲川淳二氏が、自身の「MYSTERY NIGHT TOUR 稲川淳二の怪談ナイト」20周年連続公演を記念して制定。日付は第1回の公演が1993年8月13日にクラブチッタ川崎で開催されたことから。
出所)日本記念日協会webページ
怪談や心霊を扱うテレビ番組は下火に・・・
一時期の大ブームを考えると、現在ではほとんど怪談や心霊現象を扱うテレビ番組はなくなったように感じます。
さまざまな理由があるようですが、心霊写真の多くは古いカメラ特有の「靄」(もや)が映ったり光の加減が中途半端だったりといった不鮮明なところからくるものや、残念ながら合成写真によるねつ造写真が使われていたことが発覚したことがあるようです。
つまり、カメラの性能が格段に進歩したことで不鮮明な、ある意味でそれっぽい写真が少なくなったこと、さらに一般人でもいわゆる写真加工でできるような高性能カメラが普及したことで合成写真がありふれたものになってしまい、心霊写真の需要が激減したことなどがあげられています。
また、一部、心霊から除霊などと結び付けた悪徳ビジネス(すべてが悪徳というわけではない)が流行したことで、テレビが犯罪の片棒を担ぐような番組制作をするわけにはいかなくなったという理由もあるようです。
古くから伝えられてきた話のなかに真理がある!
とはいえ、怪談や心霊がまったくなくなったわけではありませんし、そこで語られる話のなかには大切な教えが詰まっていることが少なくありません。
たとえば、「崖や橋の下の海から複数の手が出ており、海や川でなくなった人の霊が生きている人をつかまえる」といったものがあります。
諸説ありますし、さまざまなバージョンがありますが、
たとえば、夏休みに帰省中の中学生が友達と橋から川に飛び降りて遊んでいたところ一人が浮いてこなかった。
残念ながら遺体で発見された。
飛び込む瞬間を撮影していた写真には・・・、水面から無数の手が・・・
というものです。
これは、毎年のように発生する不幸な水難事故を抑制させるために、大人が子どもたちに言って聞かせる話のひとつです。
メッセージは「水を甘く見るな」「高いところから飛び込んだり無茶なことはするな」というものです。
素直に聞くことが難しい年代の子どもたちに対してこのような教訓を怪談話として伝承しているといわれています。
他にも、「廃墟」「廃坑」などでお化けがみえる、という類のものはおおむね「危険な場所なので近づかないこと」というメッセージが込められています。
このように怪談には、古くからの言い伝えや守るべき教訓といったものが織り交ぜられて伝承されてきた含蓄のある話が少なくありません。
毎年のように水難事故が発生して中高生くらいの若い生命が奪われるニュースを見るたびに、もう一度、怪談話がクローズアップされてもいいのではないかと思う今日この頃です。
また、怪談話とは少し異なりますが幼児に聞かせる「お腹を出して寝ているとカミナリ様(鬼)におへそを取られる」というものがありますが、こちらも「お腹を出して寝ていると風邪引くよ」というメッセージが込められています。
令和の夏は、含蓄のある怪談話で涼しい夏を過ごすことができたらいいですね。